BLOG北星英文ブログ

前回は「文化」について説明しましたが(前編「そもそも“文化”って何?」)、今回は文化が異なるとなぜすれ違いが生じるのかについて書きたいと思います。
文化は、もちろん、食べものばかりでなく、「誰と、何を話し、何を話さない」といったコミュニケーションのルールも含まれています。会話の習慣で言うと、日本では知らない人に話しかける習慣がないため、海外で電車やバスの中で知らない人から話しかけられて驚いたとか、逆に長らく海外に暮らしていたため、帰国後、つい隣に座っただけの初対面の人に話しかけて気味悪がられたなど、会話ルールの違いをもとにしたすれ違いの例は枚挙にいとまがありません。また、アメリカでホームステイした際に、ホストマザーが「息子は3回目の結婚でとても幸せになって良かったわ。1度目と2度目の奥さん達はいろいろ問題があったけど、この前結婚したメアリーはとってもいい子なのよ・・・」などと日本では短期間、家に世話になっているだけの他人には決して話さないような内容の「ぶっちゃけ話」をしてきて、どんな反応をすれば良いのかわからず、困ってしまった・・・という話もよく聞きます。このように、会話のルールや解釈は文化ごとに結構異なっているので、お互いに相手の言葉が理解できたとしても話の意図を完璧に理解することは案外難しいと言えます。

異文化コミュニケーションで摩擦が起きるのは、会話のルールや解釈以外にも様々あります。例えば、「友人」は韓国語では「친구(チング)」となりますが、この2つの言葉の意味するところは同じではありません。日本での友達関係は簡単に言うと、「親しき仲にも礼儀あり」ということわざに代表されるように、友達と言っても相手に迷惑をかけないように気をつけつつ遠慮がちにじっくり時間をかけて心理的距離を縮めていくのが基本ではないでしょうか。言いたいことがあっても人間関係を壊すのが怖くて言えないなどということもよく聞く話です。
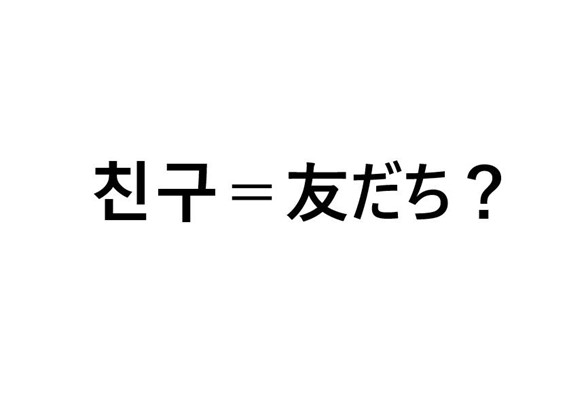
交換留学生として日本の大学で1年間過ごした韓国人学生が、「日本の生活はとても充実していたけど、残念だったのは一人も友達ができなかったことです」と書き残していたことを知って日本人のクラスメイト達が皆ものすごく驚いたという話を聞いた事がありますが、これも友達概念の違いから来るすれ違いの例と言えます。日本の学生達は、留学生とお昼ご飯を一緒に食べたり、たまに一緒にカラオケに行ったりするなど、日本の基準では十分「友達」といえる行動をしていたので、当然自分たちは友達だと思っていたのに、留学生の方は、自国の友達づきあいを基準に考えて、日本の「薄く、軽く付き合う文化」の付き合い方では、とても友達とは感じられなかったということのようです。
筆者の例では、アメリカ留学中、韓国人、台湾人、日本人の3人でルームシェアしていたところ、眉毛がすぐに凍るほど寒いある日の夜遅くに、韓国人のヤンシンさんの友達が彼女に電話をかけてきました。しばらく話をしていたヤンシンさんは電話を切るなり、「友達がさみしいから来て」と言ってるから、といいながらコートを着始めました。筆者と台湾人のルームメートが驚いて「こんな夜中に一人で行くなんて、危ないよ。ここは、アメリカだよ!!」と必死に止めましたが、彼女は「友達が呼んでいるんだから行くのが当然。行かなかったら友達じゃないし、私だってほんとにさみしかったら、夜中でも友達を呼ぶ」と断言して、吹雪の中一人で歩いて友達のところに行ってしまいました。さて、皆さんなら、この話を聞いてどう思うでしょうか。日本育ちの人は、大抵、ヤンシンさんの友達が非常識だと考えるようですし、「なんて思いやりのない、自己中の友達!自分なら、「来て」と言われたら、怒りを感じるし、友情は多分そこで終わる」というのが、ある学生の反応でした。

この「友達」以外でも「妻」「夫」「子供」「長男」「長女」「上司」「部下」「先生」「生徒」など社会的な役割の意味合いや、それに付随して期待される役割行動は文化の中で作られているため、場所が異なれば当然異なっています。そうなると、海外で「良い上司」のつもりで一生懸命振る舞っているのに、現地の人から見たら「ダメ上司」だったとか、国際結婚したら子育て方針の違いで大げんかになったり、優等生だった日本人学生が留学先では自分の意見が全く言えずに落ちこぼれ扱いになるなど、役割行動の解釈の違いが文化摩擦の種になることも多いようです。
ここまで読んで、異文化コミュニケーションが結構難しいことを少しは理解していただけたでしょうか。実は、異文化コミュニケーションが難しいのは、他にも理由があります。ここでは、自文化(自民族)中心主義(ethnocentrism)の問題を取り上げてみましょう。自文化中心主義とは、自分の文化の視点で外の世界を見て、否定的に判断したり、低く評価することを指しますが、先ほどの例で言うと、韓国の皆さんが日本の友達づきあいについて「ずいぶん冷たい人間関係だな」と思ったり、日本の学生が韓国に行って、「なんだかみんな遠慮も全然無くてえらく厚かましいな」と思ったりするのも実は「自文化中心主義」の例といえます。とはいえ、自文化中心主義はこのような「軽量級」のものばかりではありません。世界中で繰り返されてきた、宗教や価値観の違いを元にした戦争や虐殺などの悲劇も、元をたどれば自分たちのほうが他者よりも優れているといった自文化中心主義的な発想が元になっていると考えることもできるでしょう。

このように、自文化中心主義は地球上の平和を乱す元凶といえますが、実は、地球上の人間はみんなが大なり小なり「自文化中心主義」で、そこから抜け出すことはなかなか難しいのです。どこかで生まれて一定期間同じ場所で育てられた場合、その土地の習慣や考え方といった「文化」を学習するし、そうなると、当然ながら自分の慣れ親しんだ文化の視点からしか外の世界をみることができなくなります。その上、外の世界のやり方に対しては「おかしい」とか「遅れている」などと一面的な判断をしてしまうのが人間です。すなわち、みんなが自文化中心主義の地球上では、自分の文化を中心にして事の善悪や正しい行動を判断している人が多数派なので、国連その他の国際組織でなかなか話がまとまらないのは当然ですし、文化を超えて移動することが日常的になった今日の世界では、世界中で「文化の違い」が元ですれ違い、論争、そして紛争が起きています。

このように、無意識のうちに人は自文化中心主義的な思考に陥りがちであるので、大切なことは、自分が自文化中心主義的な判断をしがちであることをしっかり理解しておくことです。自分の目が自文化中心主義によって曇っているということに気づきさえすれば、自分の判断に「待った」をかけることもできるし、「おかしいぞ」とか「こんな考えじゃダメだ」と自分にダメ出しをすることもできます。こんな風に、自分の判断の偏りに気づくことができれば、異文化コミュニケーション能力の獲得に向けて一歩進むことができたといえるのではないでしょうか。読者の皆さんには、ぜひこのような「セルフ突っ込み」の癖をつけてみてはいかがでしょうか。