News
短期大学部 生活創造学科 風戸 真理 准教授 が、民族学・人類学研究の最高拠点となる研究機関誌『季刊 民族学 195号』に論文を、国立民族学博物館の広報誌『月刊 みんぱく 12月号』にコラムを寄稿しました。
ともに風戸准教授が研究対象としているモンゴルについての内容となっており、「開発支援から生まれるみやげもの-モンゴルのフェルト小物にみる脱地域化」と題した論文と、フィールドワーク時の食事についての巻末連載「ぱくっ!とフィルめし」に、モンゴル牧民の食事についてのコラムを寄せています。
美しい書影と写真いっぱいの楽しい論文となっております。
両誌とも本学図書館に所蔵されていますのでぜひご覧ください。
2026年02月25日
本学社会福祉学部 心理学科 村井 史香 専任講師が、3月6日に書籍を出版されました。
書名:自己の仮面性の心理学-小学生から大学生までの「キャラ」を介した友人関係に関する研究
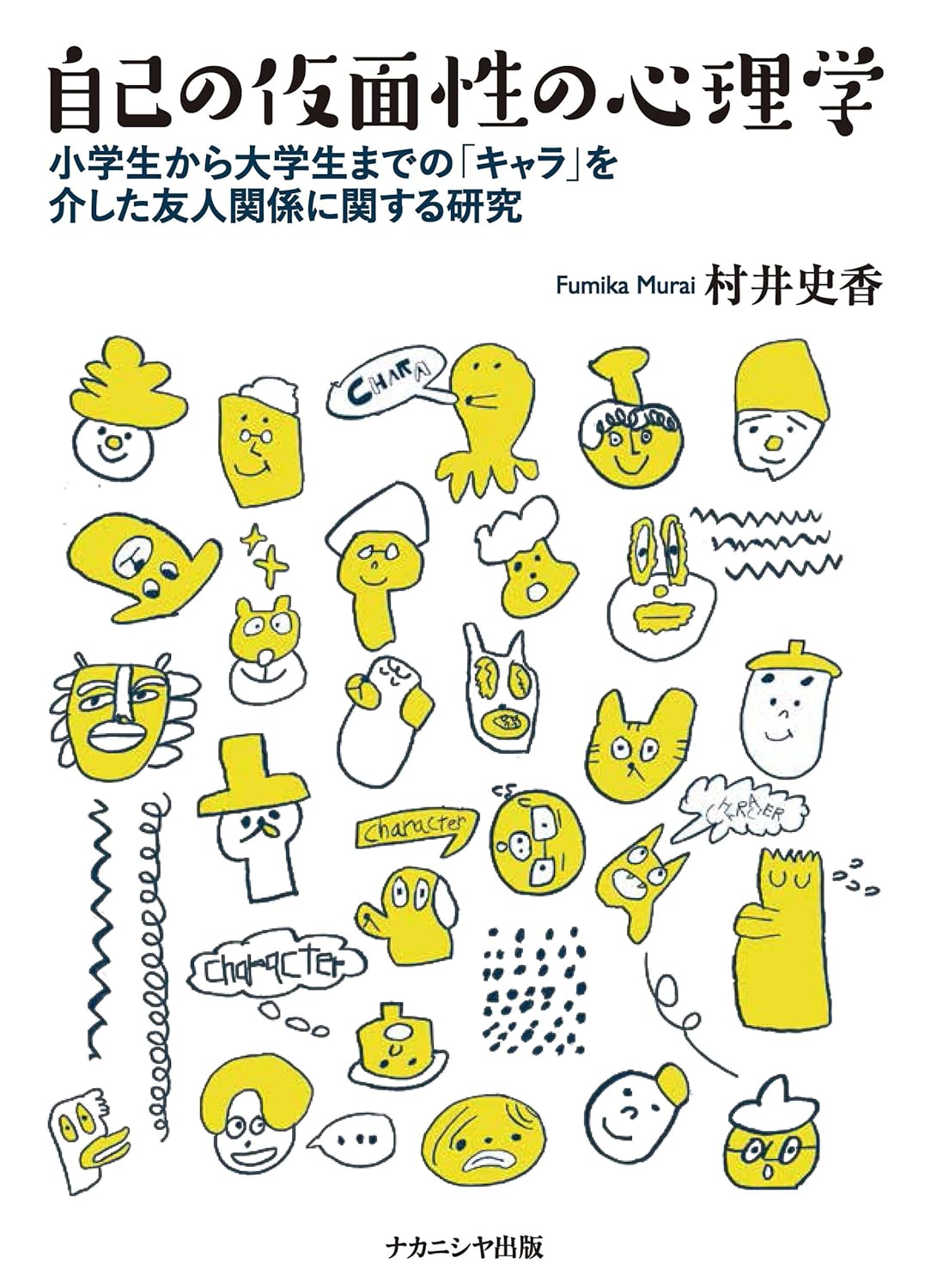
自己の仮面性の心理学-小学生から大学生までの「キャラ」を介した友人関係に関する研究
自分の「キャラ」を作って演じることは、友人関係に適応的か? 不適応的か? 小学生から大学生までを対象とした大規模調査から迫る。
※出版社HPより
詳細はこちら(ナカニシヤ出版HP)をご覧ください。
2026年02月25日
北星学園大学短期大学部は2025年度の入学生から新入生の募集を停止しており、2025年度の卒業式をもって、おおよその在学生が卒業となります。
このことを一つの区切りとして、本学に関わってこられた卒業生・教職員の皆さまとともに、これまでの歩みや思い出を振り返り、懐かしく語り合う場として、卒業祝賀会と並行して「フェアウェル・パーティ」を開催する運びとなりました。
年度末のお忙しい時期ではありますが、ぜひご出席いただきたくご案内します。
対象:北星学園女子短期大学・北星学園大学短期大学部を卒業された方
北星学園女子短期大学・北星学園大学短期大学部に勤務されていた教育職員・事務職員の方
日時:2026年3月13日(金)16:00~18:00(15:30受付開始)
場所:ニューオータニイン札幌(札幌市中央区北2西1)
会費:お一人様5,000円〔2020年度~2023年度入学の方はお一人様3,000円〕
お申込み・お問い合わせ:こちらから
・卒業生の方:https://forms.office.com/r/h0A07BWnGf
・旧教職員:https://forms.office.com/r/SfsuZc4i8V
※短大の卒業生で旧教職員の方は、旧教職員としてお申し込みください。
申込締切:会場の都合により、一次締切を2026年2月23日とさせていただきます。
申込者の人数に鑑み、二次締切を設定させていただきますこと、ご理解いただけましたら幸いです。
申込締切:2026年3月6日(金)とさせていただきます。
〔お問い合わせ〕
北星学園大学事務局 越田(こした)
011-891-2731(※お電話でのお申し込みはできません)
2026年02月20日
2026年度 一般選抜(Ⅰ期)・大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)の合格発表を行いました。
発表直後は、アクセスが集中してつながりにくい場合があります。その場合は、しばらく時間を置いて再度確認してください。
Web出願サイトのマイぺージから確認してください。
合否照会サイトから確認することができます。
※確認の際に「受験番号(アルファベット+数字5桁)」と「誕生月日(例3月2日→0302) 」が必要です。
〈合格発表の諸注意〉
2026年02月20日
2026年度 一般選抜(Ⅱ期)の出願を受付しております。
入学試験要項はこちら
※入学試験要項には、出願手続や入学試験当日の注意事項などが記載されています。
出願前に必ず確認してください。
*2学科まで併願ができます。
*大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)との併願も可能です。
出願に際してご不明な点等がありましたら、本学入試課(代表:011-891-2731)までご連絡ください。
(平日 9:00~17:00 ※11:30~12:30を除く)
2026年02月19日
文学部 山本 範子 教授 が、文藝春秋発行の月刊誌『文學界 2026年3月号』に寄稿しました。
特集「海外文学の現在地」に、筆名である、立原 透耶 名義によるエッセイ『「書いてはならない」ことを書く――中国のSF作品について』が掲載されています。
2026年02月18日
2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)の出願を受付しております。
入学試験要項はこちら
※入学試験要項には、出願手続や入学試験当日の注意事項などが記載されています。
出願前に必ず確認してください。
Web出願の登録期間は下記の通りとなります。
出願に際してご不明な点等がありましたら、本学入試課(代表:011-891-2731)までご連絡ください。
(平日 9:00~17:00 ※11:30~12:30を除く)
2026年02月16日
北星学園大学大学院では、以下の要領で「大学院研究生の募集要項」を配布しますので、お知らせいたします。
*出願は、窓口受付としますが、郵送でも受付ます。この場合は、締切日必着となります。
【問い合わせ先】
〒004-8631 北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1
北星学園大学 教育支援課 教務係 大学院担当
電話番号 011-891-2731(代表)
平日 8:45~11:30、12:30~17:00 ※土・日・祝日は窓口閉鎖
アーカイブ